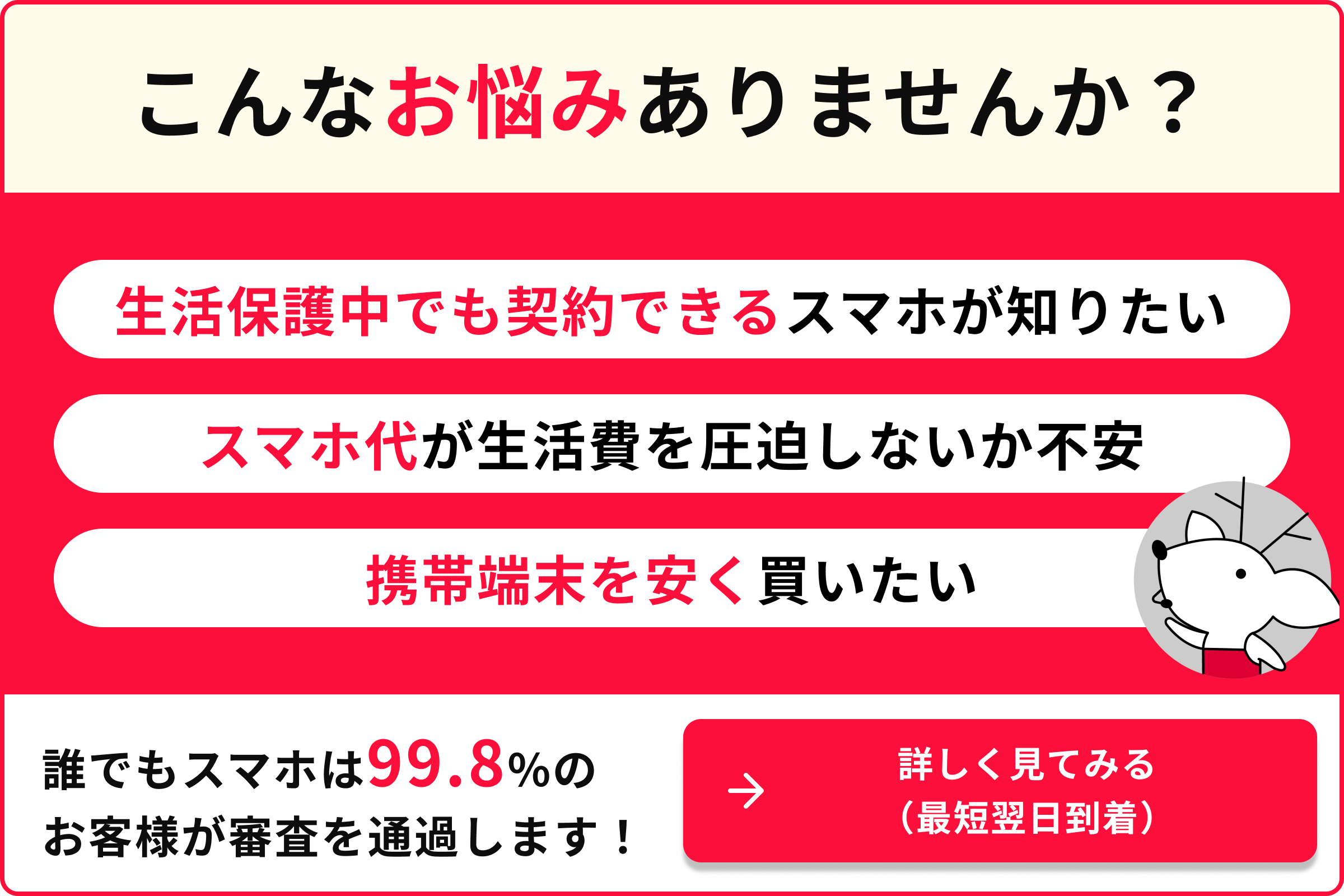- ホーム
- おすすめ情報を発信!誰でもスマホコラム
- 生活保護でできないこと、してはいけないことは何?デメリット・メリットを含め徹底解説
生活保護でできないこと、してはいけないことは何?デメリット・メリットを含め徹底解説

生活保護は、生活困窮者が健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう保障する制度です。
・失業により貯蓄が底をついてしまった
・病気やケガなどにより働けなくなってしまった
・母子家庭で生活が苦しい
など、様々な理由で生活に困っている人は、生活保護を受給できる場合があります。
しかし、「生活保護を受けるとできなくなることや、デメリットがあるのでは?」などの不安から、申請をためらっている方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、生活保護を受給するとできなくなることや、生活保護のデメリットについて解説します。
あわせて、生活保護を受給していてもできることも紹介しますので、申請を検討している方は参考にしてみてください。
目次
生活保護受給中にできないこと・してはいけないこと

生活保護の受給中にできないこと・してはいけないことはおもに以下の4つです。
生活保護受給中にできないこと・してはいけないこと
- ・生活に不要と思われる高級品の購入・保有
・資産の保有
・ローンや借金の返済
・ケースワーカーの指導に従わないこと
※ここでは、生活保護に関する一般的な基準・考え方を解説しています。受給者の状況や自治体によっては判断が異なる場合もあるので、詳しくはお住まいの地域の福祉事務所やケースワーカーに相談してください。
生活に不要と思われる高級品の購入・保有
生活保護受給者は、利用できる資産を生活のために活用する義務があります。
つまり、生活に不要な資産はすべて処分(売却など)して生活費に充てる必要があるということです。
そのため、以下のような物品の購入・保有は基本的にできません。
高価な装飾品(時計やアクセサリー)
生活保護受給者でも、腕時計や最低限のアクセサリーなど、生活に必要とみなされる物品であれば購入・保有できます。
ただし、一般的に”ぜいたく品”とみなされるような高価な腕時計やアクセサリーは、売却すれば生活費にできるため、保有が認められない可能性が高いと考えられます。
生活保護の打ち切りや保護費の返還などにつながるリスクがあるため、”ぜいたく品”の保有を隠したまま生活保護の申請をすることはやめておきましょう。
2台目以降のスマホ
携帯・スマホの2台持ちはあまり一般的とは言えないため、認められない場合があります。
とくに、端末の価格が高い場合は、生活保護制度の趣旨に沿わないと判断されて保有が認められないことがあるので注意してください。
ただし、仕事のために必要など、やむを得ない事情があれば許可される場合もあります。
判断に迷う場合は、担当の福祉事務所やケースワーカーに相談してみましょう。
資産の保有
生活保護受給者は、以下のような「資産」を売却・処分して生活費に充てることが求められています。
車・バイク(※条件を満たしていれば所有可能)
自動車やバイクは、資産とみなされることや、継続的に維持費が必要になることから、原則として保有が認められていません。
ただし、公共交通機関の利用が著しく困難で、通勤・通院に自動車が必要な場合など、一定の要件を満たす場合、保有が認められることもあります。
2024年12月には生活保護受給者の自動車の利用に関する条件が一部緩和され、買い物など日常生活での利用も場合によっては可能となりました。
地域の状況や、受給者の健康状態などによって判断が異なるため、申請時に相談してみましょう。
参考:「生活保護問答集について」の一部改正について(厚生労働省)
持ち家・土地などの不動産
活用していない持ち家・土地などの不動産は、原則として売却することが求められます。
住んでいる家または土地は基本的にそのまま保有可能ですが、利用価値と比較して売却価値が非常に大きい場合は、売却が必要になることもあるので注意してください。
たとえば、世帯人数と比較して大きすぎる家に住んでいる場合、売却して賃貸住宅などへの移転が求められることがあります。
必要以上の現金・預金
生活保護は生活に困窮している人向けの制度のため、必要以上の現金や預金は持つことができません。
貯金は全くできないわけではありませんが、厚生労働省の定める「最低生活費」以上の貯金があると、生活保護の申請ができない場合もあります。
ただし、保有してもよい現金や預金の具体的な上限額が決まっているわけではありません。
生活保護中の貯金について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
貯蓄型の保険
貯蓄型の保険とは、解約すると保険料を支払った期間に応じて解約返戻金が受け取れる保険のことです。
解約返戻金は生活費として利用できるため、貯蓄型の保険の継続は基本的にできません。
生命保険や医療保険、学資保険への新規加入
生活保護受給者が医療サービスを受けるのにかかった費用は、「医療扶助」として直接医療機関に支払われるため、本人が負担することはありません。
そのため、医療保険への新規加入は認められない可能性が高いと考えられます。
生命保険への加入も、資産形成につながるため基本的に認められません。
また、学資保険も「貯蓄型」の保険のため、加入が認められない可能性が高いでしょう。
株券などの有価証券
株券、国際証券、投資信託の受益証券などの有価証券も、資産形成につながるため取得・保有が認められません。
生活保護の申請時に有価証券を保有している場合は、一部の例外(譲渡制限のある非上場株式など)を除き、処分する必要があります。
ローンや借金の返済
ローンや借金があっても生活保護の申請はできますが、生活保護費からローンや借金の返済をすることは、原則として認められません。
そのため、生活保護申請時にローンや借金がある場合は、まず自己破産などの債務整理を行うのが一般的です。
ケースワーカーの指導に従わない
生活保護受給者は、福祉事務所または担当のケースワーカーからの指導・指示に従う義務があります。
ケースワーカーの指導に従わない場合、生活保護が打ち切られる場合もあるので注意してください。
\行政からのご紹介多数/
生活保護のデメリット

生活保護は、生活困窮者のセーフティネットとなってくれる制度ですが、以下のようなデメリットもあります。
生活保護のデメリット
- ・生活の制限を受ける・自由にお金を使えない
・親族への連絡により受給が知られてしまう可能性がある
・クレジットカードが取得しづらくなる
・ローンが組めなくなる
・ケースワーカーとの定期面談の必要がある
生活(住居・資産など)の制限を受ける・自由にお金を使えない
生活保護は生活困窮者に最低限度の生活を補償するための制度なので、受給中は自由にお金を使うことができません。
たとえば、住居は家賃が「住宅扶助」の支給範囲内に収まる物件を選ぶ必要があります。
また、資産とみなされるものや、資産形成につながるものの購入・保有は基本的に認められません。生活保護受給中でも仕事をすることはできますが、収入を得たぶん保護費は減額されるので注意してください。
親族への連絡により受給が知られてしまう可能性がある
生活保護の申請の際は、申請者の親族に対して援助が可能かどうかの問い合わせ(扶養照会)が行われることがあります。
これは、生活保護を受けるための要件に「扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先する」という考え方があるためです。
「生活保護を申請したことを家族や親族に知られたくない」と感じる場合や、扶養照会をしてほしくない特別な事情がある場合は、申請時にその点を相談してみましょう。
クレジットカードが取得しづらくなる
生活保護受給中は、クレジットカードの新規申し込み審査に通りにくくなります。
収入が少ない、資産がないなどの理由から、支払い能力がないと判断される可能性が高いためです。
継続してある程度安定した収入がある場合は審査に通ることもありますが、申し込み前に必ずケースワーカーに相談しましょう。
生活保護とクレジットカードについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
・クレジットカードなしで格安SIMを契約したい…
・生活保護を受けているのでスマホ代を安くしたい…
・携帯ブラックで他社の審査に通らない…
こんな悩みをお持ちなら、行政とも連携して通信困窮者の方のスマホ所持を支援している「誰でもスマホ」がおすすめです。
コンビニ決済と口座振替でも支払いできるので、クレジットカードが持てない方でも契約できます。
\コンビニ支払いOK/
ローンが組めなくなる
生活保護受給者は、ローンを組むことができません。
生活保護費をローンや借金の返済に使うことは、原則認められていないためです。
また、生活保護受給中の借金は収入とみなされるため、借入をしてもその分保護費が減額されてしまいます。
ローンを組む必要があるほどの大きな買い物が必要と感じる場合は、どのように資金を準備したらよいかケースワーカーに相談してみましょう。
ケースワーカーとの定期面談の必要が出てくる
生活保護受給者は、年に1度「資産報告書」を提出する必要があります。
また、家計状況の把握や自立支援のために、担当の「ケースワーカー」との定期面談や電話調査も年に数回行われます。
面談の頻度は自治体や各世帯の状況によって異なりますが、要請があった場合は必ず従わなければなりません。
ケースワーカーとの面談に応じない場合、生活保護の打ち切りにつながることもあるので注意してください。
生活保護受給中でもできること

生活保護受給者は自由にお金を使えないというデメリットがありますが、生活のすべての面が制限される訳ではありません。
生活保護受給中でも、以下のようなことであれば自由に行えます。
生活保護受給中でもできること
- ・趣味を楽しむ
・スマホやインターンネットの利用
・労働や就職のための勉強
・福祉サービスの利用
・少額の貯金
趣味を楽しむ
生活保護受給中でも、趣味を楽しむためにある程度のお金を使うことができます。
ガーデニングや読書、釣り、ジョギングやウォーキング、ゲームなど、あまりお金をかけなくても楽しめる趣味を持てば、生活がより豊かになるでしょう。
ただし、趣味に使うお金は生活費にあたる「生活扶助」から捻出する必要があります。
趣味にお金を使い過ぎて生活費が圧迫されないよう、じゅうぶん注意してください。
スマホやインターンネットの利用
スマホやインターネットはいまや情報収集に欠かせないものとなっており、生活必需品とみなされるため、生活保護受給中でも利用できます。
スマホやパソコンの購入費用や毎月の通信料金は「生活扶助」から支払う必要があるため、「格安SIM」などできるだけ安いサービスを選びましょう。
過去の料金未払いなどが原因でスマホの審査に通らない方は、携帯ブラックでも契約できる「誰でもスマホ」を利用するのがおすすめです。
労働や就職のための勉強
生活保護のおもな目的は生活困窮者の自立支援なので、労働や就職のための勉強をしたい場合は、そのための費用を支給してもらうこともできます。
就職のために資格の取得が必要な場合は、「生業(せいぎょう)扶助」として資格取得にかかる費用を負担してもらうことも可能です。
生業扶助の適用には条件があるので、資格取得を考えている場合はケースワーカーに相談してみましょう。
福祉サービスの利用
生活保護受給者が介護や支援など福祉サービスの利用を必要とする場合は、「介護扶助」の利用を申請すれば本人負担なしで利用できます。
費用が生活保護費の範囲内に収まるようであれば、老人ホームへの入居も可能ですが、生活保護受給者を受け入れるかどうかは施設によって異なるため、事前に確認が必要です。
老人ホームへの入居を考えている場合は、ケースワーカーに相談すれば予算内で入居できる施設を探してもらえる場合もあります。
少額の貯金
生活保護受給中でも、目的によっては少額の貯金が認められる場合があります。
自立後の生活資金、家電の買い替え費用など合理的な理由がある場合は、貯金をしても問題ないと判断されることが多いようです。
ただし、数十万円以上など高額な貯金があると不正受給とみなされる可能性もあるので注意してください。
生活保護受給中の貯金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
生活保護受給中のできること・できないことに関するよくある質問
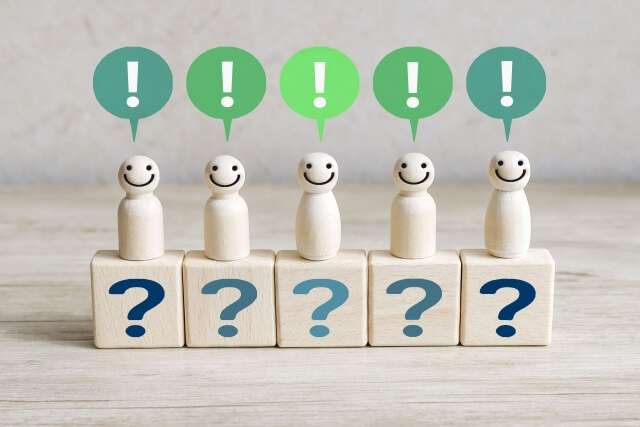
最後に、生活保護受給中にできること、できないことに関するよくある質問や気になる点に回答します。
旅行はできる?
原則として、生活保護受給中でも旅行が禁止されることはありません。
ただし、観光など単なる遊興を目的として海外旅行に行く場合、かかった費用が収入認定されて保護費が減額されることもあるので注意してください。
自治体によっては、旅行前に旅行先(宿泊先)や旅行の目的、費用、費用の準備方法などについて届け出が必要になる場合もあります。
トラブルを避けるために、旅行を計画する際はまずケースワーカーに相談しましょう。
アルバイトはできる?
生活保護受給中でも、アルバイトをすることは可能です。
ただし、収入に応じて保護費が減額されることを覚えておきましょう。
アルバイトの収入が月に15,200円未満であれば、全額が控除されるため保護費は減額されません。
収入が15,200円を超えた場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
ペットは飼っても良い?
生活保護を受給しながらペットを飼育することは禁止されていません。
生活保護受給前からいるペットはそのまま飼い続けることができますし、受給中に新たに飼い始めることもできます。
「生活扶助」の範囲内でペットを飼育している限り、手放すよう指導されることはないでしょう。
お酒を飲んだり、タバコを吸ったりしても良い?
お酒を飲むことや、タバコを吸うことも問題ありません。
ただし、お酒やタバコの購入代金は「生活扶助」から支出する必要があります。
飲み過ぎ・タバコの吸い過ぎで生活費が圧迫されないよう、節度を守って楽しみましょう。
「誰でもスマホ」は行政からも紹介多数。生活保護検討中でも安心して申し込める!
\行政からのご紹介多数/
生活保護受給中は、資産の保有や借金が認められないなど生活がある程度制限されますが、できることもたくさんあります。
趣味を適度に楽しむ、ペットを飼うなど生活を楽しみつつ、状況が許すなら再就職・自立を目指していきましょう。
生活保護の申請を機にスマホプランの見直しをお考えなら、生活保護受給者の方にも多くご契約いただいている「誰でもスマホ」の利用がおすすめです。
誰でもスマホは行政と連携して通信困窮者の方のスマホ所持を支援している格安SIMサービスで、他社の審査に通らない方もお申し込みいただけます。
月額料金は24時間かけ放題込みで2,948円(税込み)~と格安で、生活保護費を有効に活用可能です。
契約を検討している方向けの電話サポートも用意していますので、分からないこと・不安な点がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

早稲田大学を卒業後、大手通信会社の代理店で営業経験を積み、2013年に株式会社アーラリンクを創業。「誰でもスマホを持てる世の中」を目指し、携帯ブラックの方やクレカを持たない方でも利用可能な「誰でもスマホ」をリリース。現在では累計契約者数52,000人を突破している。2020年・2021年にはベストベンチャー100に選出され、社会課題の解決を軸に挑戦を続けている。
© 2022 誰でもスマホ